歯周病治療で大切な歯を守りましょう

Yスマートデンタルクリニックでは、患者様ご自身の歯をできるかぎり残すために、きめ細やかな歯周病治療を行っています。
歯周病は多くの方がかかっているとされ、国民病ともいわれています。
また、痛みの症状がなく進行するため、重度になるまで気づかない方が多いことも歯周病の大きな特徴です。
そのため、歯周病は歯を失う一番の原因といわれています。
歯周病は治療だけでなく、プロフェッショナルケア、セルフケアの両方をうまく連携させ予防や症状の安定を図ることが重要な病気です。
こちらのページでは、歯周病治療の内容についてご紹介します。
-
目次
こんなお悩みありませんか?
- 歯周病治療とは何か知りたい
- 歯周病を治療したい
- 歯肉から血が出る、腫れている
- 口臭を改善したい
- 朝起きると口がねばねばする
- 当院での歯周病治療内容を知りたい
歯周病とは
歯周病は、歯肉から血が出ているのにもかかわらず放置している場合、次第に歯が揺れる、膿が出るといった悪化の仕方をします。
歯周病に気づくことは難しいため、早い段階で歯科の定期検診に行き、原因となるプラークや歯石を取り除く必要があります。
また、歯肉の下で起こっている炎症を視覚的に確認することが難しいことも歯周病の特徴です。
歯周病の原因
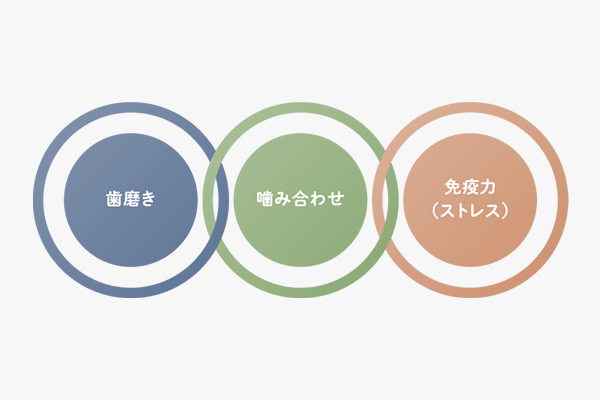
歯周病の原因は大きく分けて3つが関わっていると考えています。
「歯磨き」「噛み合わせ」「免疫力(ストレス)」です。
口には歯周病菌と呼ばれる悪性の菌が存在しています。
毎日歯磨きをしていても、正しく汚れを落とせていないと口腔内環境が悪化し病原性の強い菌が増えてしまいます。
手入れされていない川に菌が繁殖していくイメージです。
また、噛み合わせが正しく行えていないと咀嚼・歯ぎしりの際に、不適切な力がかかり動揺し始めます。
すると歯を支える骨の間が広ってしまい、細菌が侵入しやすくなってしまいます。
そこへ、精神的なストレスが加わると免疫量が低下し、歯周病菌に抵抗しづらくなります。
つまり、日々の歯磨きを心がけストレスを無くし、歯に負担をかけない噛み合わせにし、負のスパイラルを断ち切る必要があります。
歯周病の症状
Yスマートデンタルクリニックの
歯周病治療におけるポリシー

当院では、プラークを除去する口腔清掃だけでなく「噛み合わせを整える治療」も必要に応じて行なっております。
歯槽骨を溶かすものはプラーク中の毒素ですが、細菌がより元気になってしまうような口腔内環境の悪さを取り除き、負のスパイラルを断ち切ることが大切だと考えています。
総合的に口腔内環境を良くし、全体を見渡した歯周病治療をご提供させていただきます。
●正しい歯磨き
プラークを除去し、口腔内を清潔に保ちます。
プラークは最短1日で作られ始めるといわれており、その前に除去することが大切です。
しかし、歯を磨いていても磨き残しがある場合、その部分にはプラークが何日も残ることになり歯周病の進行を手助けします。
正しい磨き方で磨くことが重要です。
●噛み合わせを整える
噛み合わせが悪いと、咀嚼・歯ぎしりなどのときに不適切な力がかかり動揺し始めます。
そして、歯と歯を支える骨の間が広がり細菌が侵入しやすくなります。
噛み合わせを整えることで、歯周病になりにくい口腔環境を目指します。
歯をあまり磨いていないのに歯周病になりにくい方もいらっしゃいます。
歯周病の発症、悪化にはそのほかの口腔環境も深くかかわっているからだと考えられます。

●免疫力(ストレス)の改善
ストレスがあると血管が収縮して免疫力が低下し歯周病菌に抵抗しづらくなります。
また、ストレスは唾液の分泌量を減らします。
ドライマウスは歯周病を悪化させる要因の1つです。
●TCHの改善
TCHとは「Tooth Contacting Habit」(歯列接触癖)の略で、上下の歯を接触させる悪癖のことをいいます。
人間の歯は平常時、上下の歯が離れています。
この上下の歯が接触する時間は、食事の時間と合わせて1日に20分程度だといわれています。
これが長くなってしまうと、筋肉の疲労や顎関節の負担、歯のすり減りなどが起こります。
当院では、このTCHの改善に力を入れています。
Yスマートデンタルクリニックの
歯周病治療の内容

●歯周病検査
当院では原則として初診時に歯周病検査を行っています。
お口の中の状態をきちんと把握することで、その方に合わせた治療計画ができます。
また、検査の数値を比較することで、治療の成果やゴールもわかりやすくなります。
根本から改善するための丁寧な治療をご提供させていただきます。
●歯周病治療
・スケーリング
当院の歯科衛生士が、振動が少なく、痛みの出にくい超音波スケーラーを使用してプラークや歯石除去をします。
定期検診のときにも行う基本的なプロフェッショナルケアです。
・ルートプレーニング
超音波スケーラーや手動のスケーラーを用いて、より細かい部分や目に見えない歯肉の中の歯石を除去します。
この「歯肉縁下歯石」と呼ばれる歯石が歯肉の上につく歯石よりもさらに強固に付着し炎症の原因になっています。歯石を取り除いた後、歯の根の表面をツルツルにすることで歯石がつきにくくなります。
ご自宅でこれを取り除くことはできないため、歯医者での清掃が必要となります。
歯石を取り除いたあと、歯の根の表面をつるつるにすることで歯石をつきにくくする処置も行います。
●咬合のコントロール
必要に応じて、噛み合わせの調整や片側ばかりで噛むといった悪い口のくせの改善を行います。
不適切な力がかかり、動揺によって歯と歯槽骨の間に細菌が侵入しやすくなることを防ぎます。

●歯磨き指導
歯医者でのケアだけではお口の中の健康を保つことが難しいため、ご自宅でのケアも大切です。
ご自宅での歯磨きを正しく行えるよう、歯磨き指導をさせていただきます。
また、歯間ブラシやフロスなど、歯ブラシ以外の口腔ケアグッズの使用もご提案いたします。
●フラップオペレーション
スケーリングやルートプレーニングを行っても歯周病に改善が見込めない場合、歯肉を切開し目視下で歯石や悪くなった歯肉を取り除くことがあります。
著しく歯周病が進行しているときに行われる処置です。
●SPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)
治癒とはいえなくても、症状が安定した歯周組織の状態を維持していくための処置です。
目的が治癒か安定かの違いで、この中にもスケーリングやルートプレーニング、咬合のコントロールが含まれます。
歯周病の進行のない、寛解状態を保つための処置です。
●マウスピースでのアプローチ
歯ぎしりが歯周病に悪影響を及ぼしている場合、マウスピースでの治療になることもあります。
歯周病治療後のメンテナンス
歯周病治療はそのあとのメンテナンスが大切です。
メンテナンスとは治療が終わったあとに継続して、良い状態を維持することをいいます。
そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口の清掃を定期的に行います。
最低でも半年に1回は定期的にチェックを受けましょう。
進行した歯周病の治療が終わった方は、1~3か月のサイクルで来院し安定した歯肉の状態を管理していくことが大切です。
再発予防のために行うこと

●定期メンテナンス
歯医者で行う定期的なメンテナンスです。
・症状がある場合、噛み合わせのバランスを整える
歯は日々動いています。
そのため、一度噛み合わせを整えても、くせや力のかかり方によって変わってしまうことがあります。
・力のコントロール
お口の中では、さまざまな部位がさまざまな機能を分担することによってバランスが保たれています。
そのため、どこか一部に強い力がかかっている場合や筋肉に緊張がある場合は、そのバランスはすぐに崩れる可能性があります。
過剰に力がかかっているところはないか、定期検診で診ることができます。
・食いしばり、歯ぎしりの予防
食いしばり、歯ぎしりは、ストレスと密接な関係にあるといわれています。
また、ご本人にとって不快な噛み合わせがあることによっても起こると考えられています。
原因を見つけ出し噛み合わせを整えるといった、食いしばり、歯ぎしりが起こらないようにメンテナンスを行います。
・マウスピースでのコントロール
「噛み合わせを整える」「ストレスを除去する」などを行っても食いしばりや歯ぎしりが続いてしまうことがあります。
その際はマウスピースを装着していただき、歯や筋肉の安静を図ります。
・TCHのコントロール
人の上下の歯が接触している時間は、1日のうち20分ほどだといわれています。
ほとんどの時間、人の歯は噛み合っていません。
噛み合っていない正常な状態を維持できるようコントロールします。

●セルフケア
ご自宅で行っていただくメンテナンスです。
・ブラッシング
歯ブラシを使った口腔清掃です。
歯医者でのケアだけでは、歯周病治療後の良好な状態を長く保つことはできません。
ご自宅でのケアが何よりも基本になります。
・歯間ブラシ、フロス
歯間は磨きにくく、汚れの残りやすい部位です。
歯間ブラシやフロスを使い、清潔を心がけましょう。
よくある質問
-
痛みはないのですが、歯周病といわれました。治療しなければいけませんか?
-
歯周病は痛みなく進行します。
痛みが出るときは重度であると考えられています。
痛みや症状がなくても積極的な治療が必要です。
-
若年者でも歯周病にかかることはありますか?
-
30歳からが好発年齢といわれています。
また、一種の免疫疾患としての若年性の歯周病というものも存在します。
気になることがあれば歯医者に相談しましょう。
-
歯周病がひどくなり揺れた歯は抜かなくてはいけませんか?
-
当院ではなるべくご自身の歯を残すような処置を心がけています。
他院で抜かなくてはならないといわれた歯でも残せる可能性があります。
ぜひ一度ご相談ください。
しかし、その歯を残すことで、まわりの歯や組織に悪影響を及ぼす場合は、残すことが難しいケースもあります。
-
喫煙者です。
タバコと歯周病の関係を教えてください。
-
タバコを吸うと歯肉の血流量が減り、歯周病が悪化しやすくなります。
喫煙によるドライマウスも増悪因子です。
また、喫煙者は歯周病が悪化しても気づきにくいといわれています。
減ってしまう血流量に関係しているためです。
歯周病の治癒を目指す場合は、禁煙がおすすめです。
-
定期検診に通うことが大変です。
-
セルフケアで落とせる汚れは全体の60%ともいわれています。
歯医者での定期検診で、定期的に細かいところの汚れを落とし歯周病を予防しましょう。
著者 Writer

- 吉本 博
- 【資格】院長・歯科医師
診療案内
MEDICAL

一般歯科
一般歯科では、虫歯や歯周病に対する治療をおもにおこないます。
中でも「痛みのない治療」「可能な限り歯を抜かない治療」を得意としています。
患者様にとって最善の治療を提供できるようカウンセリングにも力を入れています。

予防歯科
近年では痛みが出てからの治療ではなく「痛みを発生させないための予防治療」が大切とされています。
どれだけ丁寧に歯磨きをしていても、歯には汚れが残っています。
予防歯科ではセルフでは取り除けない汚れをプロの手によって除去していきます。

審美歯科
審美歯科は歯の美しさを追求する治療で、代表的なものとして「ホワイトニング」が挙げられます。
当院ではその他にも「ラミネートべニア」や「セラミック」「ダイレクトボンディング」といったさまざまな治療をご用意しています。

小児歯科
幼少期の歯の健康は、大人になってからの歯に強く影響します。
長く健康的な歯でいられるためにおこなう子どもへの治療を小児歯科と呼びます。
当院では子どもが歯医者を通いやすいような取り組みに力を入れています。

口腔外科
口腔外科の治療で知られているものは「親知らずの抜歯」ではないでしょうか。
その他にも実は「インプラント」や「顎関節治療」もこの口腔外科の診療科目に分類されます。
当院ではお口の機能面・審美面どちらもバランスの取れた治療をご提案します。

歯周病治療
歯周病は自覚症状がみられた時にはかなり重症化が進んでいます。
「歯ぐきから血が出る・しみる」といった症状がみられる場合は歯周病の可能性があります。
当院では原因となっている歯石の除去を丁寧におこない改善を図ります。

虫歯治療
歯を失う原因の多くが「虫歯」になります。
当院ではマイクロスコープといった最新の機器を使用して長く歯を残せるような治療をご提案します。
治療の痛みが苦手な方にも麻酔を施してからおこなうなどして、不快感の少ない治療を心がけています。

根管治療
根管治療とは歯の神経に達した虫歯に対しておこなう処置を指します。
根管治療は非常に高度な技術が求められる治療ですが、当院では最新の機器を導入し施術にあたっています。
患者様の歯をなるべく抜かないような治療をご提案します。

義歯・入れ歯
良い入れ歯を手に入れるためには、医師の技術と技工所との連携がとても重要です。
当院では権威のある技工所と提携し、患者様のお口に馴染みやすい入れ歯・義歯の提供をしています。
入れ歯・義歯の提供だけでなく、使い方やお手入れ方法も丁寧にお伝えします。

インプラント
インプラントは歯の機能性・審美性の両方を追求した治療法です。
1本から対応できる治療で、治療の際に他の歯を削ることがほとんどないため、健康的な歯をそのまま維持できることもメリットです。
患者様がしっかりと治療内容を理解できるよう、説明も丁寧に行います。

ホワイト
ニング
当院のホワイトニングは、光照射を必要としないホワイトニングをおこなっています。
ホワイトニングの効果を最大限に発揮するために、治療前の歯の清掃にもとても力を入れています。
患者様のライフスタイルに合わせて最適な審美治療を提案します。

ボトックス
治療
ボトックス治療は、ボツリヌス菌と呼ばれる菌を活用し筋肉にアプローチします。
顎関節症や噛み合わせ不良に対して良く行われる治療の1つです。
身体の状態によっては治療がおこなえない方もいらっしゃるので丁寧な治療説明をいたします。
当院のご紹介
ABOUT US
Yスマートデンタルクリニック
- 住所
-
〒252-0232
神奈川県相模原市中央区矢部3-17-15
- 最寄駅
-
JR「矢部」駅 徒歩1分
- 駐車場
-
提携コインパーキングあり
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00〜12:30 | ● | ● | ✕ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ✕ | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
- お電話でのお問い合わせ
-
042-704-8217



